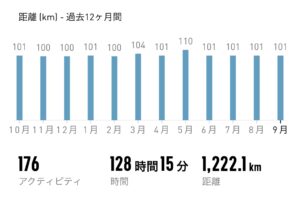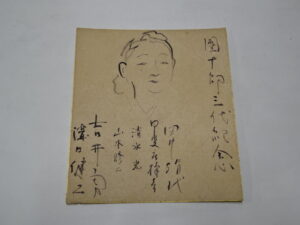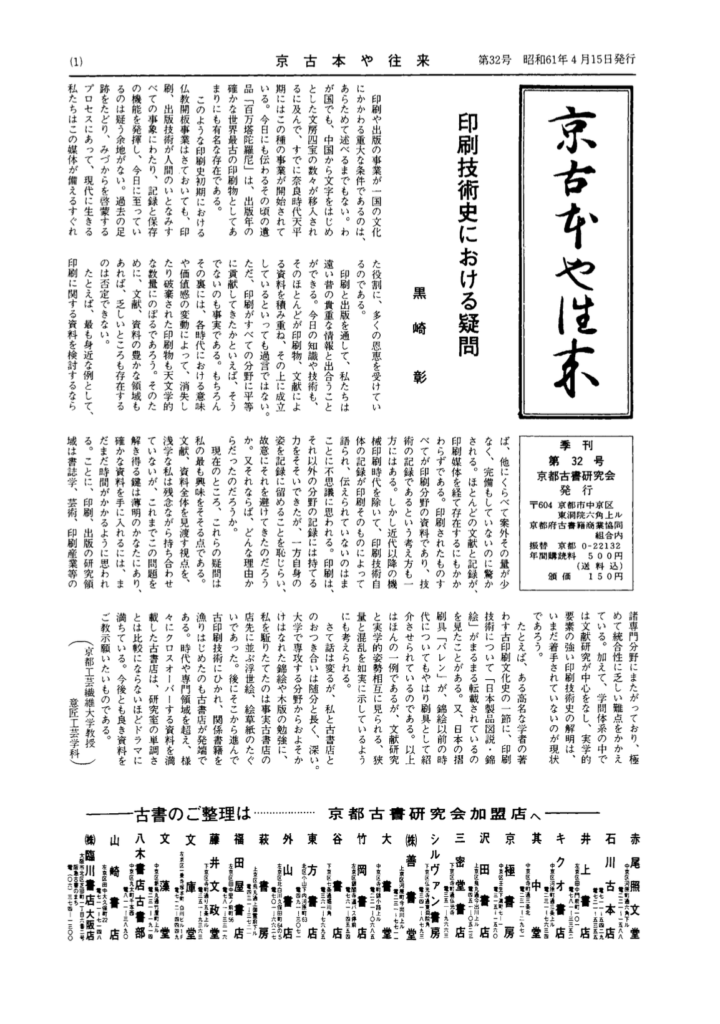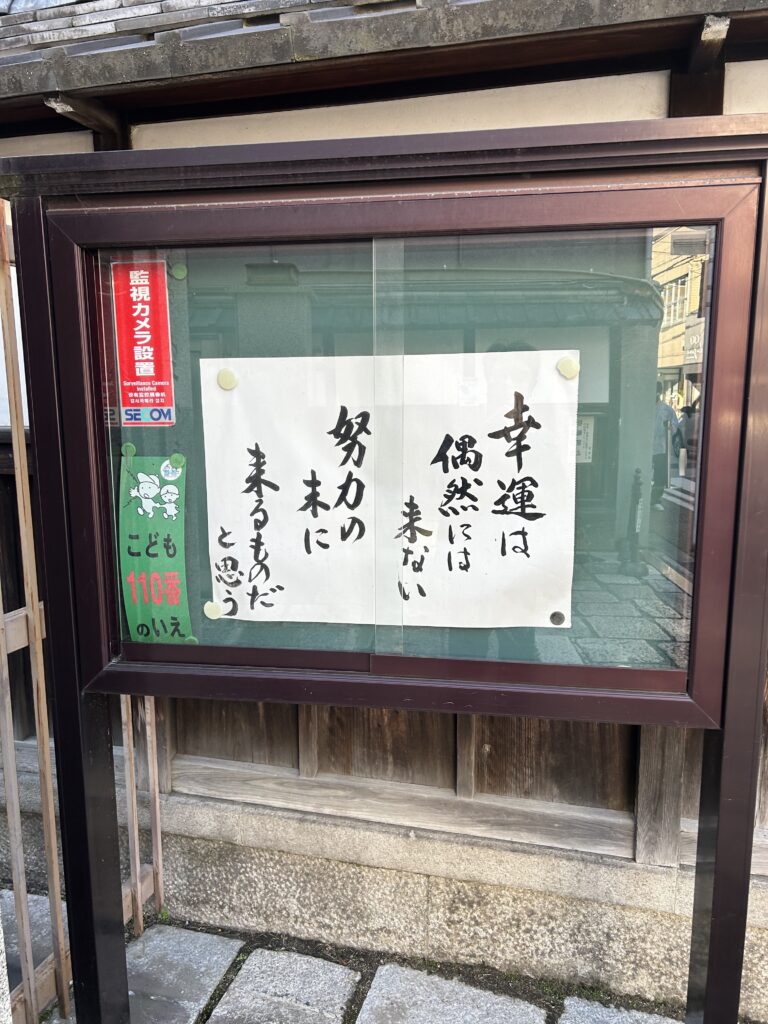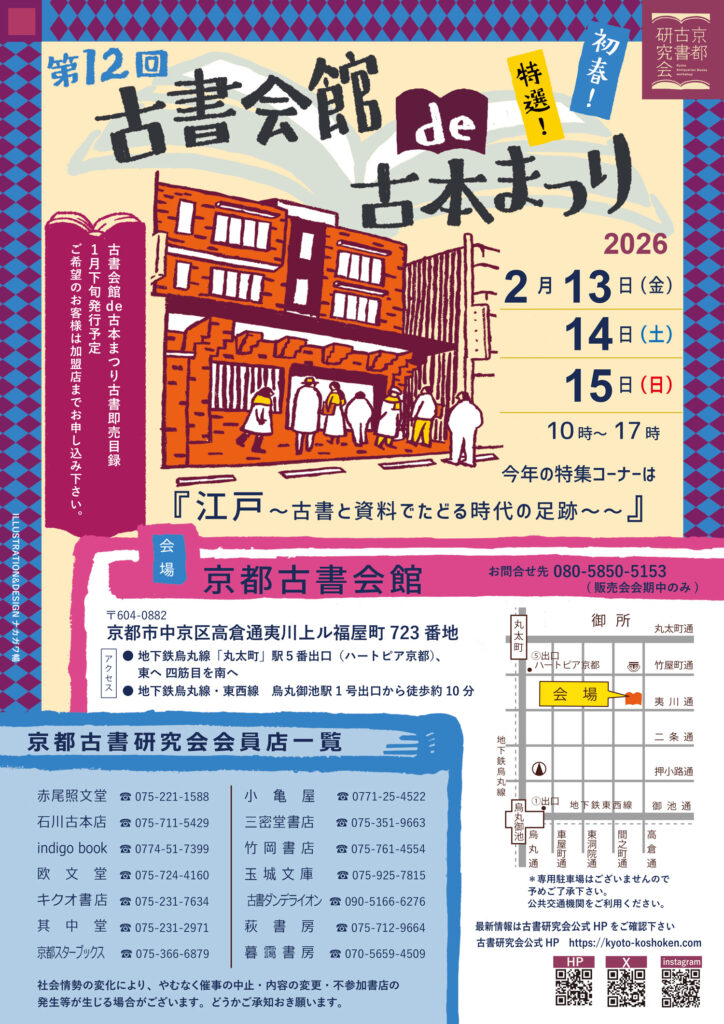正しく自転車に乗りましょう
正しく自転車乗ってみましょう 其中堂 三浦
自転車乗りが戦々恐々としている、来年4月からの自転車の青切符化。これまで、かなりルーズに運用されてきた自転車の道交法違反が、きつく取り締まられるようになります。
筆者は、運搬用自転車の運転歴45年のベテランドライバーですから、いろいろなシチュエーションがあるのがわかっています。
それにもとづき、現在はポリシーを立てて運転することとしています。
1・安全が第一
1-1・ヒヤリハットにならないよう周りに気を配る
2・周囲の交通を円滑にさせる
3・道交法は、1と2にもとづき、遵守する
3-1・安全上問題なしと判断できるときは、柔軟に対応する
3-2・特に、街なかで、人とクルマが多数交錯する場所では、法よりも安全と円滑な交通を優先する
4・以上のポリシーに反するような交通行為をするものには、ベルや動作で非難することを躊躇しない
まぁ、自転車運転をされない方には具体的になにを言っているかわからないかもしれませんが、いまの法律では、自動車と違ってお巡りさんに捕まらないので、善悪・正邪の判断は運転者に任されていると言ってよく、それぞれの運転者がそれぞれのポリシーで自転車に乗っている現状なのです。
それが、来年4月から、自動車運転と同じように、お巡りさんに捕まってしまうわけです。つまり、運転の判断基準の第一に道交法遵守が来るわけです。
そうなると、
1・道交法が第一
2・安全が第二
3・交通の円滑化は第三
つまりは、事故が増え、自転車運転の生産性が落ちる、ということになります。
さて、実際にどう対応することになるのか、以下縷々述べさせていただきます。
1・自転車は正しい道を走る
1-1・車道の左側を走る
※さすがに、2車線以上の車道(幹線道路・準幹線道路)の右側を逆行したことはないです
安全第一なので、右側通行はお金もらっても無理です。
一方通行の道路(生活道路・京都市街部はほぼこれ)は、柔軟に右側も走りたいです。
交通円滑化に欠かすことはできません。しかし、逆走の反則金6000円が待ちかまえています。
1-2・二重線の路側帯の外側を走る
※二重線の真ん中を自転車で走るのも違法です。
1-3・自転車マーク(矢羽根)の上を走る
※自転車マークのある道ではその上を走る。(しかしながら、マークは道交法上、意味がないので、違反しても罰金はありません)
2・交差点を正しく渡る
これを完全に理解して、間違いなく渡れる人は誰もいないと思いますが。。
2-1・自転車横断帯のある交差点では、かならずそこを渡る。
※まちがっても車道を渡ってはいけません。お巡りさんが待ち構えています。
2-2・自転車横断帯がない交差点では、(原則)車道の左端を渡る
※右端渡ると違反です
2-3・横断歩道上を渡るときは、歩行者信号を守る。
道路の右側の横断歩道を渡ってもよい。(←マジ助かる)
歩行者の横断を妨げない速度で走る。
どうしても歩行を妨げそうなときは、自転車から降りて歩く(歩行者に変身)。
※右左折車の歩行者妨害の対象にはならないことに注意。
2-4・二段階右折をするときは、最初の横断後、交差点内で待つ。(←マジかよ)
※生活道路で二段階右折を強いられるのは辛すぎ、荷台に20kgぐらい積むとその場で90度回転なぞ無理ゲーです。
2-5・ 歩車分離信号の交差点
・車道信号を守る場合は、道路の左側を進む。
・歩行者信号を守る場合は、2-3を遵守して横断歩道を横断する。右側の横断歩道もOK。
・スクランブル信号でない場合は、もちろん斜め横断は絶対ダメ。ふらふらと斜めもダメ!
3・歩道を走ってよいケース
3-1・子どもとお年寄りはOK!14歳~69歳乗り入れ不可!
※年寄り風を装うことにしましょうか。お巡りさんに止められたらOUTですが!
3-2・歩道の幅員が2メートル以上の場合はOK!、というのはデマ。
※でも当面は指導だけで、取り締まり対象にはならないかも?
※四条通や河原町通のアーケード商店街は年齢に関わらず、手押しのみ
3-3・車道又は交通の状況からみてやむを得ない場合
※「やむを得ない」かどうかは客観的に判断されるので、自分都合の判断が認められるとはかぎりません。
3-4・自転車通行可の標識がある歩道
※五条通や御池通のように、歩道と自転車道と分離されている場合もあります
3-5・牽引車つきの自転車(例・ヤマトの運搬車)は、自転車ではない軽車両なので、歩道は走れません。
反則金が課せられるケースが他にも多々ある(酒気帯び・並進・無灯火・二人乗り・傘持ち運転etc..、特に一旦停止違反!)ので、当然ながら注意が必要です。
一
まだまだ矛盾点の多い自転車の青切符ですが、そのうち緩いところで落ち着いてくれることを願っています。もちろん、自分都合ではなく、安全が保たれた上での交通の円滑化、が第一義であります。
くわしい事例の紹介は、警視庁の自転車ルールのページを御覧ください。
(東京都で有効な内容ですが、他府県でもおおよそ通用するはずです)
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/rule.html
クイズ形式もあります。
https://www.keishicho.metro.tokyo.lg.jp/kotsu/jikoboshi/bicycle/menu/bicycle_quiz.html
![[公式]京都古書研究会](https://kyoto-koshoken.com/wp-content/uploads/2022/10/logo-1.png)